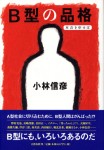黒澤明の映画をデビュー作の「姿三四郎」からリアルタイムで見てきた小林信彦がDVDで全作品を見直して書いた作品論・作家論。黒澤作品のどれを見るべきかがよく分かる本で、読んでいて僕は「野良犬」「酔いどれ天使」「わが青春に悔いなし」などを無性に再見したくなった。
20年ほど前にビデオで「天国と地獄」を見た時に「ごく控えめに見ても大傑作」と思った。完璧な映画の出来もさることながら、主人公の三船敏郎が演じる権藤という男のキャラクターにしびれたのだ。職人気質で頑固である半面、間違い誘拐の身代金を出すことを決意する権藤の在り方はほとんどハードボイルドだと思った。学生時代に名画座で「羅生門」を見た時、ラストの取って付けたようなヒューマニズムに違和感を覚えたが、「天国と地獄」ではヒューマニズムが作品と一体になっていた。ちょうどその頃、小林信彦はこの映画について「失敗作」と書いていたと記憶する。これはつまらないという意味ではなく、警察の描き方などを指した言葉だったと思う。この本の中には「文句なしに面白い『天国と地獄』」という第15章に触れてある。少し引用する。
そこでの熊井啓氏の発言は、その<問題>に関してである。仲代扮する戸倉警部が、このまま犯人をあげても刑期十五年で終ってしまうから、犯人を泳がせておいて、(共犯者二人殺しの)さらに動かぬ証拠をつかもう、と断言する件りだ。警部は犯人を極刑に持ってゆくつもりだが、犯人は計算外の動きをしてしまう。
(中略)
<何度見てもおもしろい。見るたびに新しい発見がある。>
と、ためらいなく日本人(芝山幹郎氏)が評価するのは、長い時を経てからであった。
小林信彦が高く評価する黒澤作品はこの「天国と地獄」まで。僕はこの後の「赤ひげ」にも感心したが、小林信彦は「完璧なテクニックだけの映画」としている。何か言ってやろう、何か見せてやろうというものがないからだ。
僕らの年代では封切り時に劇場で見ることができた黒澤作品は「デルス・ウザーラ」(1975年)以後だ。といっても「デルス・ウザーラ」は劇場では見なかったので、僕が実際に封切りで見ているのは「影武者」(1980年)以降の5作品にすぎない。その中で本当に感心したのは「乱」だけだった。映画は劇場で見なければいけない、というのは特にスケールの大きな黒澤作品の場合、あてはまることだが、同時に時代性というのは封切りで見ないと分からないためもある。作品的な評価だけでなく、封切り時の時代の空気を伝えるのがこの本の目的でもあっただろう。
黒澤作品のほとんどはテレビ放映時に録画したビデオを持っていたが、カビがはえたので全部捨ててしまった。DVDでそろえようかと思うが、これから買うならブルーレイの方が良いかもしれない。
【amazon】黒澤明という時代