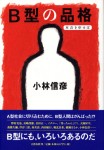「きのうの神さま」
映画監督西川美和の短編集で直木賞の候補になった。映画「ディア・ドクター」製作の過程で行った僻地医療に関する取材を元にした映画のアナザー・ストーリー。収録されているのは「1983年のホタル」「ありの行列」「ノミの愛情」「ディア・ドクター」「満月の代弁者」の5つ。どれも映画監督らしい小説だと思う。
もっとも完成度が高いのは「ディア・ドクター」で、これは映画の主人公の背景を描いた内容(だと思う。未見なので断言できない→見た。現在の状況になった背景と言って良いと思う)。脚本家や監督はキャラクターの造型の過程で映画には描かれない背景を設定することがある。それが映画に深みを与えたり、俳優が演技する際の参考になるからだ。西川美和はそれを小説にしたわけだ。あとがきによれば、映画のための取材費用を出してもらう代わりにそういう約束を編集者と交わしたそうだ。
小説「ディア・ドクター」は医師を父親に持つ兄弟の物語で、弟の視点で描かれる。父親を尊敬し、父親のような医師になりたいと思っている兄は父親に対して自分の本当の姿を見せることができない。本当の兄について弟はこう思っている。「兄は本来、決して大人からほめられるような子供ではないのだ。けた外れに活発で、馬鹿げたことが大好きで、はっちゃけていて、ぼくと二人、転がり回るようにしながら育った」。そんな兄が父親の前では緊張してしまう。父親は子供に医師になってほしいとは思っていない。人の死に対して鈍感になっている自分のようにはなってほしくないからだ。
「ぼくも、医者になろうかと思う」
すると、それを聞かされた父は、顔をかすかにゆがめ、うーん、と唸るような溜息とともにばつの悪そうな笑い方をした。そして長く黙した後、「世の中にはいろんな生き方があるからな。よく考えたほうがいい」と言葉を添えた。
その時の、深い穴のあいたような兄の表情を一生忘れないと母は言った。
兄の絶望の種はほんの些細なことである。身を焦がすほど憧れた父から、一度も「お前も医者になりなさい」と言われなかったということだ。ぼくの幸運が、兄には悲運だった。
分数計算以上の計算がダメで理系音痴の兄は密かに志望していた医学部の受験をやがてあきらめ、旅行代理店に就職。その後、医療機器メーカーに入り直すが、何度も仕事を変え、遠く離れた寒村の小さな診療所で事務の仕事をするようになる。
しかし、父親は医者にならなかった兄について語る時、「いつも遠いところに吹く、澄み切った風を望むような眼」をしていた。兄の生き方を認めているのだが、それは兄には伝わらない。兄の本当の思いも父親には伝わらない。父親を太陽のように思っている兄とその兄を心配する弟の細かい心情を鮮やかに描いて、これは素晴らしい短編だ。泣かせる話である。兄の現在がどういう状況にあるかは映画を見るべきなのだろう。これは映画を補完する物語なのだ。
「ありの行列」は小さな島で3日間だけ代理の医師を務める男の話。男は都会の病院に勤め、「オートメーション的な作業の連続」の医療業務に携わっている。島に着いたその夜、老婆に往診を頼まれる。別に悪いところもなさそうな老婆の世話をしているうちに、最初に医師を志したころの青臭い自分のことを思い出す。
流れに巻き込まれて一度青臭さを棄てた自分がいまさら青臭くなるはずはなく、今日のことも、自分にとっては今後繰り返されることのない非日常であるからこそだ。これは男にとっては仕事ではなく、お遊びである。しかし擦られるままにして、ここちよさそうなため息をついている森尾セイの素直な背中は久方ぶりの男の幼い、恥ずかしいような陶酔に目を瞑ってくれていた。
流れ作業のような都会の病院よりも僻地の診療所の方にこそ医者の本来の姿がある。西川美和はそんなことを大上段に振りかぶって言っているわけではないが、そういう視点が作品の根底にある。
収録作品に共通するのはどれも映画の1シーンのような短編であること。ヒッチコックは「人生の断面よりケーキの断面」と言ったけれども、西川美和は僻地医療にかかわる人々の人生の断面を見事に生き生きと描き出している。このシーンをつなげれば映画になるし、一つのシーンを描くために物語を設定しているように思える。ジェフリー・ディーヴァーの短編のように意外な結末を目指した小説とは作り方が根本的に違う。映画監督らしいと思ったのはシーンが中心になっている小説だからだ。
【amazon】きのうの神さま