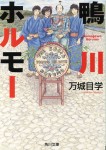「イントゥ・ザ・ワイルド」の原作。これは映画よりも感動的なノンフィクションである。著者は登山家で文筆家のジョン・クラカワー。クラカワーはアウトドア雑誌にアラスカで餓死したクリス・マッカンドレスについて9000語の記事を書いた後、マッカンドレスと自分に共通点が多いことが気になり、さらに詳細にその足跡を調べ始める。マッカンドレスが交流した多くの人たちや死体の発見者にインタビューし、アラスカの現場まで出かける。そして「向こう見ずな愚か者」「変わり者」「傲慢と愚行によって命を落としたナルシスト」という非難を退けるマッカンドレスの真の姿を明らかにする。
この本が感動的なのはマッカンドレスの生き方が感動的だからではない。著者がマッカンドレスの生き方を理解し、共感し、なぜ若者が荒野を、冒険を目指すのかを自分の体験や多くの先例を出して説明しているからだ。何よりも著者がマッカンドレスに深く寄り添っているからだ。ショーン・ペンがこの原作に感動し、映画化しようと思ったのもそこがあるからだろう。しかし、映画にはクラカワーの視点を取り入れようがなかった。いや少しは入っているだろうが、十分ではなかった。マッカンドレスの生き方とさまざな人たちとの交流は分かるけれども、荒野を目指す若者に対して、観客に共感を十分持たせるには至っていない。
原作の前半で最も感動的なのは映画でハル・ホルブルックが演じた老人との交流の場面(第6章)だ。老人は雑誌の記事のことを知り、雑誌を1冊譲ってくれと雑誌社に手紙を出してくる。その手紙を読んだ著者は老人にインタビューに出かける。
マッカンドレスは放浪の旅の途中で多くの人々に忘れられない印象をあたえていた。その大半は、彼といっしょに過ごしたのがわずか数日、長くても一、二週間にすぎなかった。しかし、男性にせよ、女性にせよ、ロナルド・フランツほど深く心を動かされたものは、誰もいない。一九九二年一月にふたりの進んでいた道が交差したとき、彼は八十歳だった。
老人とマッカンドレスの数週間に及ぶ交流は映画に描かれた通りだ。若い頃、酔っぱらい運転の車にはねられて妻子を亡くした老人はその後さまざまな若者の援助をする。年を取ってそれを辞め、孤独な生活を送っていた頃にマッカンドレスと知り合い、再び父性が頭をもたげ、援助し、養子にならないかと誘う。マッカンドレスに影響を受けた老人はマッカンドレスと別れた後に助言に従って、キャンプを体験するようになる。そんな時、ヒッチハイクをしていた若者2人を車に乗せ、マッカンドレスの死を知らされる。
「アレックスがアラスカへ出発したときに」フランツはそのときのことをよく覚えていた。「私は祈ったんだ。アレックスの肩にかけた手を放さないでください、と神に願いごとをしたわけさ。あれは特別な若者だって神に言ったんだよ。だけど、神はアレックスを死なせてしまった。それで、なにが起こったか、私は12月26日に知り、神を捨てた。教会員であるのをやめ、無神論者になった。アレックスのような若者の身に恐ろしいことをもたらす神を信じないことに決めたんだ」
後半はマッカンドレス家の事情となぜマッカンドレスが荒野へ出かけたのか、どうやって死んだのかを詳細に描く。若者が荒野を目指す理由について、著者は自分が22歳のころに行った単独登山のことを2章にわたって書く。そして死因について、明らかにする。映画では食用の植物と毒のある植物を間違って食べたからと説明されたが、原作では違う。確かに最初の記事を書いた際、著者は毒のある植物を食べたためとしていたが、その後の調査で食用の植物にもサヤの部分に毒があることが分かる。サヤにはアルカイドが含まれていた。この毒が体に入ると、「身体は食べたものを役に立つエネルギーの熱源に変えることができなくなるのだ。スウェインソニンを大量に摂取すると、たとえどんなに食べ物を胃に入れても必ず餓死するのである」。
餓死の説明は同じであっても、映画はなぜこの部分を改変したのだろう。このサヤの部分の毒に関して書いた書物はマッカンドレスが死んだ当時にはなかった。映画ではマッカンドレスが植物図鑑を見て自分が間違った植物を食べてしまったと理解する場面があるけれども、あれではマッカンドレスはやっぱり愚かな青年になってしまうのではないか。原作が出たのは1996年。その後、やっぱり間違った植物を食べたという結論になったことも考えられるが、可能性は薄いように思う。映画の描き方として、主人公が知らない植物の実態について説明しようがなかったためではないかと思われる。
あと、なぜあのバスがアラスカの荒野にあったのか、農場主のウェインが逮捕されたのはなぜかなど、映画では分からない細かい部分もよく分かった。映画にあまり興味を持てなかった人もこの原作には共感できると思う。
最後になぜ、青年は荒野を目指すのか、その重要な部分を引用しておく。エヴェレット・ルースとは1930年代にマッカンドレスと同様に荒野を愛し、そこで生き、行方不明となった若者である。
大人の月並みな関心事しか頭にない私たちにとって、若さの情熱さと憧れにはげしく翻弄されたころのことを思い出すのがいかに困難かをはっきり示している。エヴェレット・ルースの父親が、二十歳の息子が荒れ地で姿を消した何年かあとで、感慨をこめて言ったように、「年配の者には、若い者の奔放な情熱は分からない。誰にもエヴェレットの気持ちはよく理解できないと思う」
【amazon】荒野へ (集英社文庫)