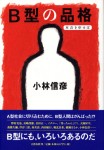「とてつもないミステリ、上陸」と大書されたオビには「ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞三冠制覇」ともある。SFの主要な賞を制覇したうえに、2008年のエドガー賞(MWA最優秀長編賞)の最終候補にも残ったそうなのである。だからSF、ミステリの両方にアピールするこういうオビになったのだろう。もっとも、エドガー賞最終候補(MWAホームページ参照)の中には「川は静かに流れ」があったので、受賞できなかったのは当然と思う。
僕はミステリとしてよりもSF3賞受賞作のつもりで読んだ。2007年、アラスカの太平洋岸に近いバラノフ島が舞台。ここは第二次大戦前にドイツで迫害を受けたユダヤ人を受け入れる土地としてアメリカが用意したが、1948年、イスラエルが建国後3カ月で崩壊したために大量の難民が流入し、人口300万人を超えている。島はユダヤ人自治区となり、シトカ特別区と呼ばれている。こうした架空の設定の下、ホテルで薬物中毒の男が殺害される事件が起きる。同じホテルを定宿にしていた酒浸りの殺人課刑事マイヤー・ランツマンが事件の捜査を始める。
設定はSFだが、SF的なアイデアの発展はない。ミステリとして優れているわけでもない。オビに書いてあるようなハードボイルドでさえない。おまけに100ページ読んでも面白くならない。上巻を読み終わっても面白くなく、下巻に入って少し面白くなったかという程度。これはこちらのユダヤ人(問題)に対する知識が不足しているためもあるだろうが、エンタテインメントを期待して読むと、途中で放り出す人がいるのではないか。ユダヤ人向けの小説なのだと思う。
下巻が面白くなるのは主人公が危機に陥るのと、殺人事件の背景、聖地に帰ろうとするユダヤ人たちの動きが出てくるからだが、これも大きく盛り上がるわけではない。タイトルの「ユダヤ警官同盟」とはユダヤ人警官のための国際的な友誼団体エサウの手のこと。この団体の会員証には捜査上の権限など何もないが、銃撃事件で停職となり、警察バッジを取り上げられた主人公は捜査のためにバッジ代わりとして苦し紛れに使うのだ。だから内容に深く関係しているわけではない。
あとがきを書いている訳者の黒原敏行は同じような歴史改変SFの例としてフィリップ・K・ディック「高い城の男」、思考実験のSFとして小松左京「日本沈没」を挙げている。僕はこの2冊のどちらも面白かった。特に前者はナチス・ドイツが勝った世界を舞台にストーリーが進行しながら、終盤に主人公が世界の揺らぎを感じる場面(ナチスが負けた世界を見る場面)があって、いかにもSFだった。ディックだから当たり前である。
作者のマイケル・シェイボンは元々は純文学作家でピューリッツアー賞も受賞しているが、純文学にとどまらず、境界侵犯的(トランスグレッシブ)小説を書いているという。本書もSFとミステリに境界侵犯した本。個人的には境界侵犯の仕方が足りないと思う。純文学的側面が優れているとも思えない。ミステリで純文学なら、ケム・ナンのあの瑞々しい傑作「源にふれろ」ぐらいの充実度が欲しくなる。SF3賞受賞もユダヤ人の力が働いたためではないかと思えてくる。
ジョエル&イーサン・コーエン兄弟が映画化の予定とのことだが、IMDB(The Yiddish Policemen’s Union )にも詳しい情報はなく、まだ計画段階。公開は2010年以降になるらしい。
【amazon】ユダヤ警官同盟〈上〉 (新潮文庫)