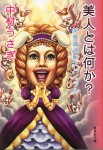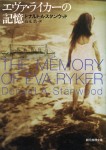早食いはなぜ肥満につながるのか。僕は早く食べることによって血糖値が上がる前に量を食べすぎるためと思っていた。人は血糖値が上がることによって満腹感を感じる仕組みになっているからだ。たいていのダイエット本にもそう書いてある。この考え方なら、一定量を食べる限り、早く食べても遅く食べても太り方は同じはずだ。
ところが、本書には「摂食量を同じにしても早食いの方が肥満傾向にある」と書いてある。なぜか。「早食いのときは、脳内にドーパミンやオレキシンが活発に分泌されて、体は貪欲にカロリーを取り込み、ため込むモードになって」いるからだそうだ。
これを裏付けるものとして、成人男子に糖尿病検査で使われる糖負荷テスト用の糖質液を飲んでもらう実験を紹介している。1回目は速やかに血糖値が上昇したが、2回目の上昇は1回目の半分、3回目には上昇しなかったという。被験者はこのブドウ糖液を飲むのが嫌になったのだそうだ。
糖の吸収はおいしいとか飲みたいといった前向きの気持ちがあるかないかで大きな影響を受けるということです。まずいな、いやだなと思いながら食事をするとカロリー吸収は抑えられるが、おいしそう、食べたいな、という前向きの気持ちで食べると、体はそれに反応して、積極的に吸収しようとするのです。
もう一つ、太らないためにはものを良く噛んで食べることが推奨される。これも血糖値の上昇速度と絡めて説明されることが多いが、この本はラットでの実験から「唾液や水分でドロドロになったものは、固形物のまざったつぶつぶのものよりも、飲み込んだあとは血糖値の上昇が小さい」としている。消化管は固形状のものが入ってくると、頑張って消化吸収しようとするのだという。
同じ量、カロリーのものを食べてもドロドロの状態の方が吸収は少ないという意外な結論だ。普通、よく噛むのは消化吸収を助けるためと言われるが、それとはまったく逆の結論なのである。だからカロリーを吸収しにくくするためには良く噛んでドロドロの状態にしてから飲み込んだ方がいいというわけ。
この2つの指摘が僕には面白かった。本書のサブタイトルは「人間だけに仕組まれた“第2の食欲”とは」。お腹いっぱいなのにデザートを食べてしまう別腹の説明など前半は脳と食欲の関係が中心、後半はダイエットに必要な知識と食全般について書いてある。具体的なダイエット法はないが、朝バナナダイエットのようにこうすれば痩せると決めつけるようなダイエット法がいかに間違っているかがよく分かる本である。ダイエットに関心のある人は読んでおいて損はない。
著者の山本隆は畿央大学大学院健康科学研究科教授。
【amazon】ヒトは脳から太る (青春新書)