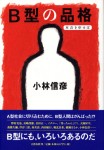鹿児島のOさんと電話で話していて、「出ましたね」と教えられた。週刊文春の連載エッセイ「本音を申せば」をまとめた小林信彦のこの本をOさんも毎年楽しみにしているのである。昼休み時間に会社のそばの大きな書店で探した。エッセイコーナーにあるだろうと見当を付けていたが、なかなか見つからない。他のコーナーも探し、再びエッセイコーナーに戻ってようやく見つけた。平積みになっていても、本が多いとなかなか見つからないのだ。大きな書店は何の目的もなくふらりと入って、たくさん並んでいる中から本を選ぶ楽しみはあるが、目当ての本を探す時には時間がかかる。こういう時、amazonに頼もうかと思ってしまう。 書店には検索機械もあったが、触っても反応しなかった。僕の操作の仕方が悪かったのか。
僕にとって小林信彦のエッセイを読む楽しみは自分の映画の見方が大丈夫かどうかを確認することにある。リアルタイムで週刊誌の連載を読んでいれば、映画観賞ガイドとしての機能もあるのだろうが、1年分をまとめて読む場合は前年に公開された映画の見方の確認が主な役割となるのだ。
内田けんじの「アフタースクール」について小林信彦はこう書いている。
ラストで、パズルのピースがみごとにはまり、全体の図(ストーリー)が完成したとき、なるほど、こういう話だったのかと感心した。<頭を使った脚本>ではあるが、それだけではない、ほのぼのとした味がある。
自分がどんな感想を書いたか気になったので、Sorry, Wrong Access: 「アフタースクール」を読み直してみる(元はmixiに書いた日記をコピーしたもの)。
個人的には大技に比べて、終盤の展開はややドラマ的に弱く、少しバランスが取れていない感じを受けた。ドラマ的な弱さは構成と関係してくるので難しいのだが、ここをもっと強化すれば、映画は完璧になっただろう。ただし、内田けんじ監督の良さはこういう軽いほのぼの感にあるのだと思う。
まあ、「ほのぼの」が一致しているのでいいだろう。しかし、この本で取り上げられたこれ以外の映画はほとんど見ていない。「接吻」「相棒 劇場版」「ICHI」「その土曜日、7時58分」など。これはDVDを借りてみようと思う。特に「接吻」が見たい(これと「その土曜日、7時58分」は宮崎映画祭で上映するけど)。ニコール・キッドマン主演で劇場公開はされなかった「マーゴット・ウェディング」も見たいと思った。
タイトルのB型に品格に関しては5回に分けて書いてある。僕は血液型による人の分類は占い程度のものと考えている。血液型の本に書いてあることが当たってるように思えるのは大まかに当てはまることしか書いてないから。アメリカなら人種や民族で分けるところを、日本はほぼ単一民族だから、こういうもので分類しないと分けようがないのだろう。もし血液型で人のタイプが分類できるというなら、環境が異なるA型のエスキモーとA型のアボリジニが同じタイプだったというような統計的データを示してほしいものだ。小林信彦自身、「この連載のために、いま出ている血液型人間学の本をパラパラ見たが、こりゃダメだと思った。A型男性はこう、A型女性はこう、という風に決めつけているからだ」と書いている。まあ、それでもここで小林信彦が書いている自分の周囲や芸人の血液型に関するエピソードは読み物として面白い。
週刊文春の連載は映画のほかに政治、世相、東京のことなどを取り上げることが多く、本書のオビに書いてあるように「クロニクル(年代的)時評」の様相が濃かった。これまでに10冊出ている本もそうだったが、今回は映画に関する文章が多い。あとがきによれば、これは「某新聞に連載していた映画のコラムをやめて、新旧の映画のことが気をつかわずに書けるようになった」ためだそうだ。
【amazon】B型の品格―本音を申せば